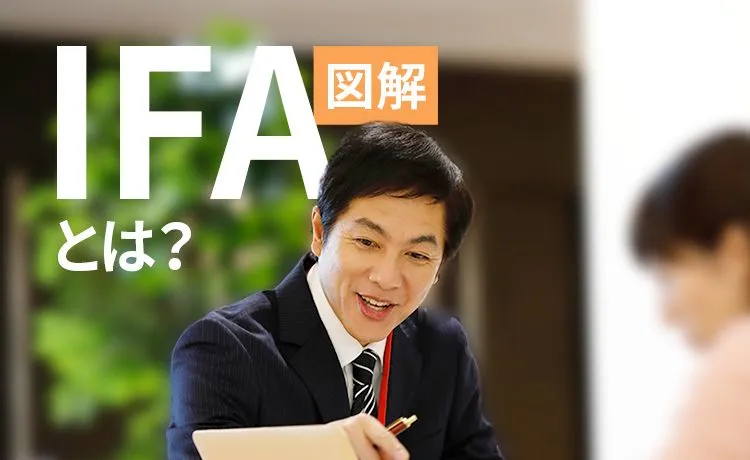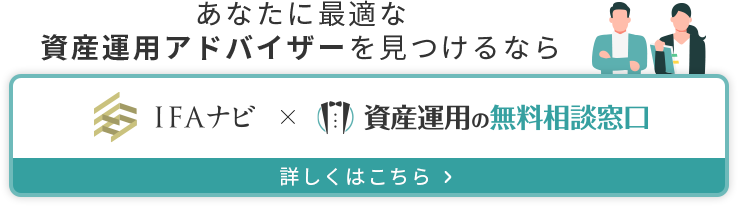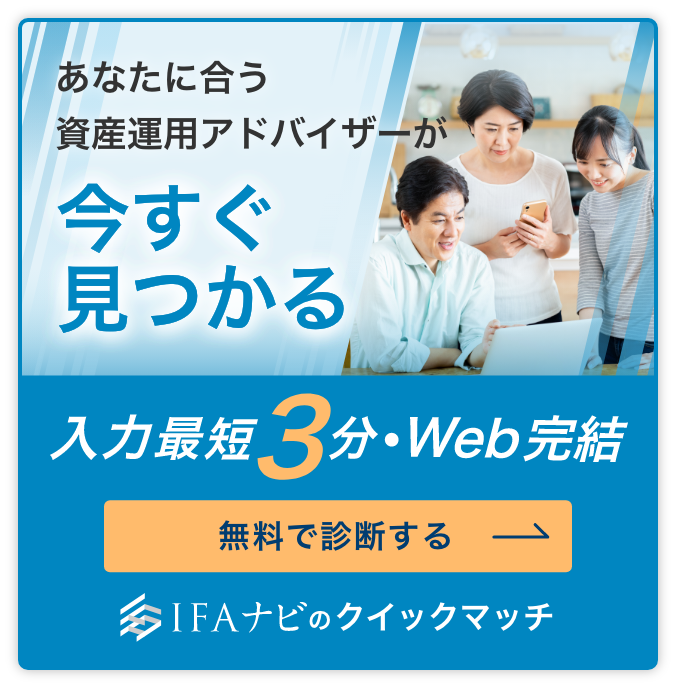閉じる
- トップ
- 【比較表あり】銀行でNISAはやめたほうがいい?4大理由とおすすめ相談先、メリット・デメリットを解説
【比較表あり】銀行でNISAはやめたほうがいい?4大理由とおすすめ相談先、メリット・デメリットを解説
![]() “銀行でNISAはやめたほうがいい”って聞いたけど、どうして?
“銀行でNISAはやめたほうがいい”って聞いたけど、どうして?
![]() NISAは、普段使っている銀行でも始められるみたいだけど、本当にそれでいいのかな?
NISAは、普段使っている銀行でも始められるみたいだけど、本当にそれでいいのかな?
NISAで積立投資をするにあたり、こんな悩みを持つ方も多いでしょう。
2014年に開始したNISA(少額投資非課税制度)は、2024年から新NISA制度へと大きく刷新されました。これに合わせ、これまでの「一般NISA」や「つみたてNISA」は、「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の2つに再編されています。
NISA制度は、長期・分散投資を非課税で行える画期的な制度です。しかし、どこでNISA口座を開くかによって、投資できる商品やサポート体制が大きく異なります。NISAの金融機関選びは、運用成果を左右する重要なポイントだと言えます。
この記事では、「本当に銀行でNISAを始めるのはやめたほうがいいのか?」という疑問に対し、理由・背景・比較・対処法をわかりやすく解説します。NISAで後悔しないための情報をわかりやすくお伝えしますので、ぜひNISAを始める際の参考にしてください。
【この記事のポイント!】
- 銀行でNISAはやめたほうがいいと言われる一番の理由は「商品の選択肢がとても少ない」から。
- NISA取扱商品数の幅広さはインターネット証券が最も豊富。手数料も安い。
- インターネット証券でも、IFAならアドバイザーに相談しながらNISA運用が可能。
目次
なぜ銀行でNISAはやめたほうがいいと言われるのか?
新NISAが始まってから、SNSやニュースサイトでも「銀行ではNISAを始めない方が良い」という意見を目にする機会が増えています。
たとえば、
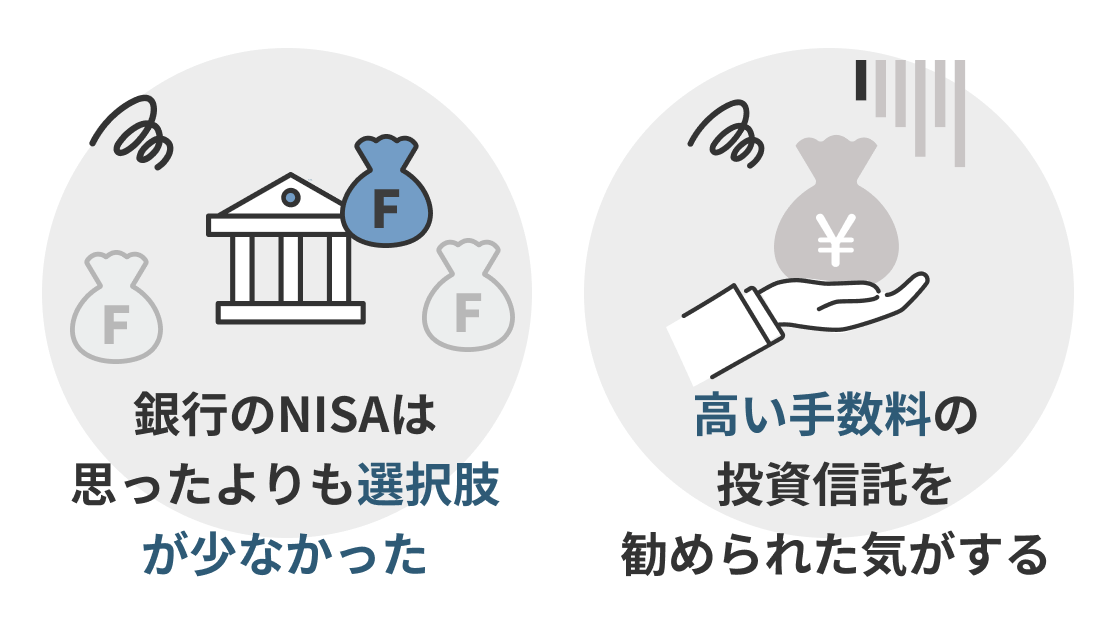
といった体験談や口コミも少なくありません。
では、なぜこのような評判が広がったのでしょうか?
その背景には以下のような要因があります。
- 銀行はNISAで取り扱う投資商品が少なく、選択肢が限られている
- 銀行では個別株やETFなどに投資できない
- 選択肢が少ないと、特定商品に誘導されていると感じやすい
こうした要因により、特に情報収集に長けた若年層やデジタル世代を中心に、「NISAを始めるなら銀行より証券会社を選ぶべき」という意見が広まっているのです。
銀行でのNISA活用にも「手続きが簡単」、「いつもの窓口で相談できる」など、初心者にとってメリットとなる点もあります。一方で、「銀行でNISAはやめた方が良い」という評判の原因となるデメリットがあるのも事実です。
次章では、銀行でNISAはやめたほうがいいと言われる4つの具体的な理由を、それぞれ詳しく解説します。
銀行でNISAはやめたほうがいいと言われる4つの理由
NISAを始める際、「銀行はやめたほうがいい」と言われるのはなぜでしょう。ここでは主な4つの理由を挙げ、それぞれ詳しく解説します。
選べる投資信託の種類が少ない
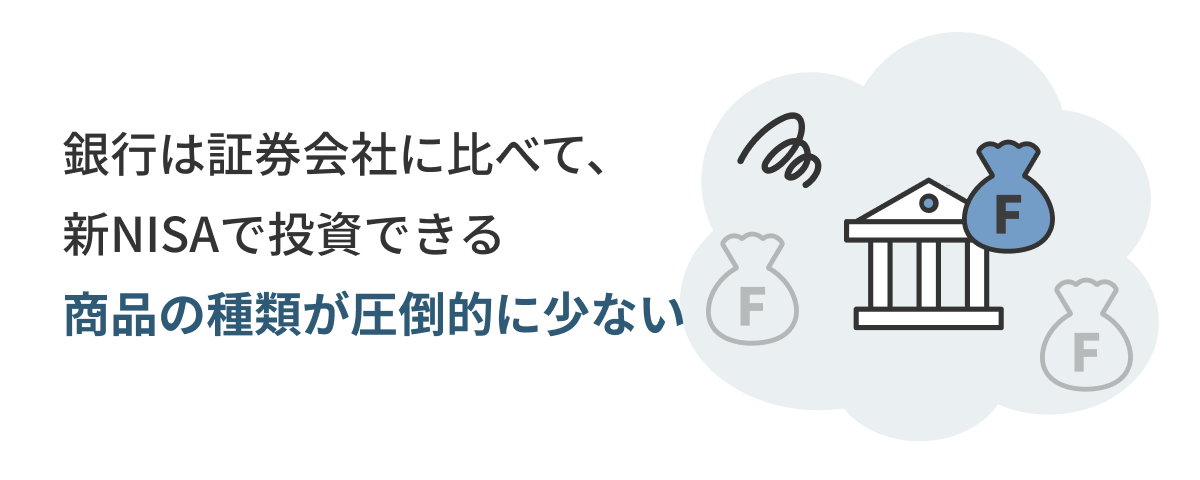
「NISAを銀行で始めるのはやめたほうがいい」と言われる最大の理由は、銀行は証券会社に比べて、新NISAで投資できる商品の種類が圧倒的に少ないからです。
NISA制度ではお得に金融商品へ投資できますが、実は、どの金融機関でも同じ商品が買えるわけではありません。つみたて投資枠・成長投資枠ごとに金融庁がNISAの対象商品や対象銘柄を定めており、その中から各金融機関がそれぞれの方針で独自のラインナップを決めているのです。
そのため、場合によっては、「あなたが投資してみたいと思っていた投資信託がA証券にはあるけどB銀行にはなかった!」ということも十分あり得ます。NISA口座は1人につき1口座しか開設できませんから、その金融機関の商品ラインナップを事前にしっかりと確認することが重要です。
では、金融機関ごとの取扱商品数は、具体的にどれくらい異なるのでしょうか。
下記の『主な金融機関のNISA対象商品取扱数一覧』を参考にして下さい。
| つみたて投資枠 | 成長 投資枠 |
||
|---|---|---|---|
| 大手ネット証券 | SBI証券 | 271本 | 1,409本 |
| 松井証券 | 272本 | 1,189本 | |
| マネックス証券 (NTTドコモグループ) |
264本 | 1,249本 | |
| 三菱UFJ eスマート証券 (旧:auカブコム証券) |
259本 | 1,170本 | |
| 楽天証券 | 267本 | 1,367本 | |
| 大手対面証券 | 大和証券 | 36本 | 201本 |
| 野村證券 | 20本 | 476本 | |
| みずほ証券 | 12本 | 75本 | |
| 大手銀行 | みずほ銀行 | 16本 | 130本 |
| 三井住友銀行 | 4本 | 97本 | |
| 三菱UFJ銀行 | 24本 | 395本 | |
| ゆうちょ銀行 | 15本 | 62本 | |
| りそな銀行 | 20本 | 103本 |
- ※2025年6月23日時点
- ※出所:新NISAナビ
一覧を見ると、特に、つみたて投資枠の対象となる投資信託の取り扱い本数は、大手ネット証券が200本以上を取り扱うのに対し、銀行では数十本程度と大きな差があることが分かります。
せっかくNISAを始めるのであれば、なるべく多い選択肢の中から、自分に合う最適な商品に投資したいものです。このようなNISA対象商品取扱数の少なさが、「銀行はやめたほうがいい」と言われる大きな一因となっています。
株式やETFに投資できない
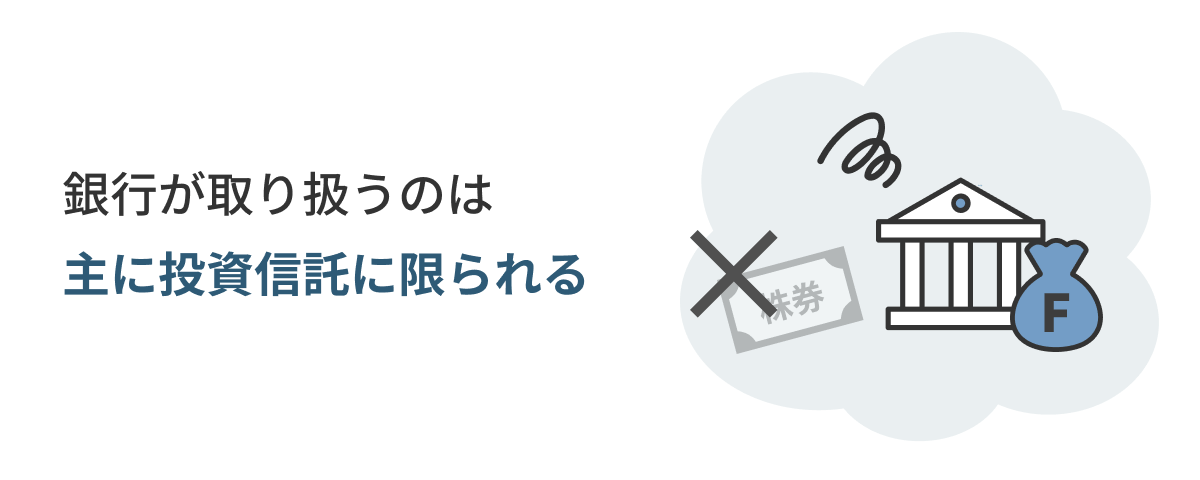
「NISAを銀行で始めるのはやめたほうがいい」と言われる理由の一つに、銀行では株式投資ができないことが挙げられます。
新NISA制度には「つみたて投資枠」と「成長投資枠」があり、成長投資枠では投資信託の他に、個別株式やETF(上場投資信託)への投資も可能です。株式投資は、保有していると株式優待を受け取ることができる銘柄もあるため、一部では非常に人気のある投資商品です。
例えば、成長投資枠であっても、「数カ月ごとに一定金額ずつ株式を購入する」と決めて投資すれば、自分が好きな株式銘柄で実質的な積立投資を行うことができます。
しかし、銀行では原則として、これらの株式やETFを直接購入することができません。銀行が取り扱うのは主に投資信託に限られるため、成長投資枠を利用しても、その選択肢は投資信託のみとなる場合がほとんどです。
一方、証券会社では個別株やETFの取引が一般的であり、多様な投資機会を提供しています。もしあなたが「個別企業の株式にも投資してみたい」、「ETFにも興味がある」と考えているのであれば、銀行のNISA口座ではそのニーズに応えられない可能性があります。株式投資も視野に入れている方にとって、この点は銀行NISAの大きなデメリットとなり得ます。
金融商品の手数料が高い場合がある
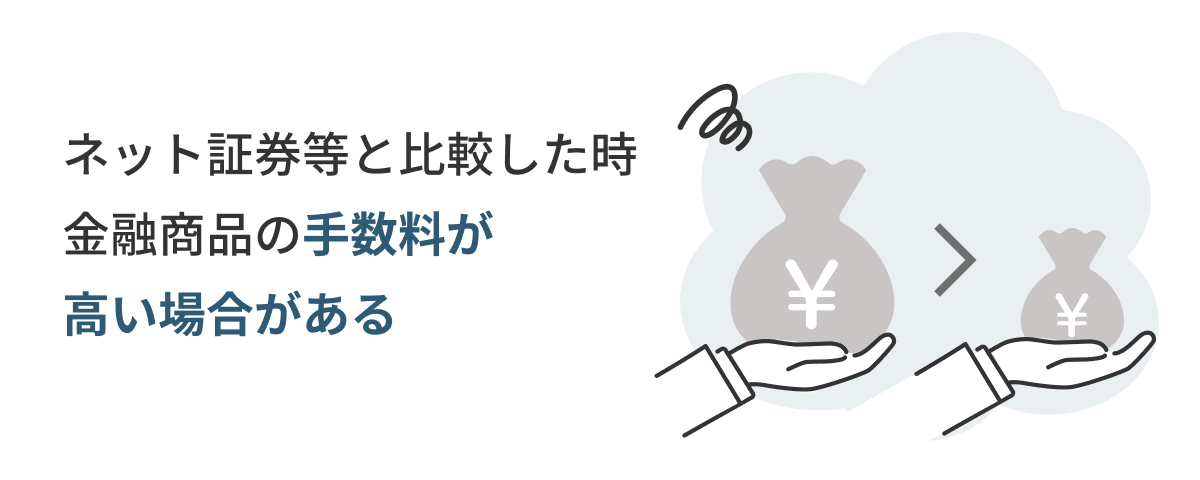
銀行でNISAをするのがおすすめできない理由には、特にネット証券と比較した時に、金融商品の手数料が高い場合がある事も挙げられます。
NISA制度は、運用益にかかる税、つまり儲けが出たときにかかる税が非課税になる制度です。NISA口座自体は無料で開設できますが、商品の買付時等には費用がかかります。
NISA口座での投資にかかる主なコストは、以下のとおりです。
具体的に、NISAでかかる手数料には以下の種類があります。
- 購入手数料(販売手数料):商品を購入する際にかかる手数料です。
- 信託報酬(運用管理費用):商品を保有している間、継続的にかかる手数料です。
- 換金手数料(信託財産留保額):商品を売却する際にかかる手数料です。
これらの手数料に関して、銀行とネット証券の一般的な傾向を比較すると以下のようになります。
銀行の場合
- 購入手数料:「つみたて投資枠」で選べる投資信託は、どの金融機関でも基本的に購入手数料はかかりません(ノーロード)。しかし、「成長投資枠」で取引できる個別株や、一部の投資信託には購入手数料がかかる場合があります。また、銀行が取り扱う成長投資枠の商品には、ネット証券に比べて購入手数料がかかるものが多く、料率も高めな傾向があります。
- 信託報酬:銀行が取り扱う投資信託は、ネット証券で取り扱っているものと比較して、信託報酬(運用管理費用)が高い傾向にあります。
- 取扱商品数:ネット証券に比べて、NISAで選べる金融商品の種類や数が少ない傾向があります。そのため、低コストで運用できる商品を選びたくても、選択肢が限られてしまうことがあります。
ネット証券の場合
- 購入手数料: 「つみたて投資枠」はもちろんのこと、「成長投資枠」で投資信託を購入する場合も、ほとんどのネット証券で手数料が無料(ノーロード)です。個別株の売買手数料も、銀行に比べて無料や低コストのところが多いです。
- 信託報酬:業界最低水準の低コスト投資信託(インデックスファンドなど)を多数取り扱っており、手数料を抑えて運用しやすい環境が整っています。
- 取扱商品数:非常に多くの種類の投資信託や個別株、ETFなどを取り扱っており、投資家の選択肢が広いです。
なぜ銀行は手数料が高い傾向があるのか
銀行は、店舗を構え、対面での相談サービスを提供しているため、その分の人件費や運営コストがかかります。これらのコストが、金融商品の手数料に上乗せされる傾向があると言われています。一方、ネット証券は、店舗を持たず、オンラインでの取引がメインであるため、運営コストを抑えられ、その分手数料を低く設定できるというメリットがあります。
NISAの非課税メリットを最大限に活かすためには、手数料を抑えることが非常に重要です。特に長期で運用するNISAでは、わずかな手数料の差でも、運用期間が長くなるほど総額に大きな違いが出てきます。
もし手数料を重視するのであれば、一般的にはネット証券でのNISA口座開設が推奨されます。対面での相談やサポートを重視したい場合は銀行も選択肢になりますが、その場合は手数料について十分に確認し、納得した上で金融商品を選ぶことが大切です。
最低積立金額が高いケースがある
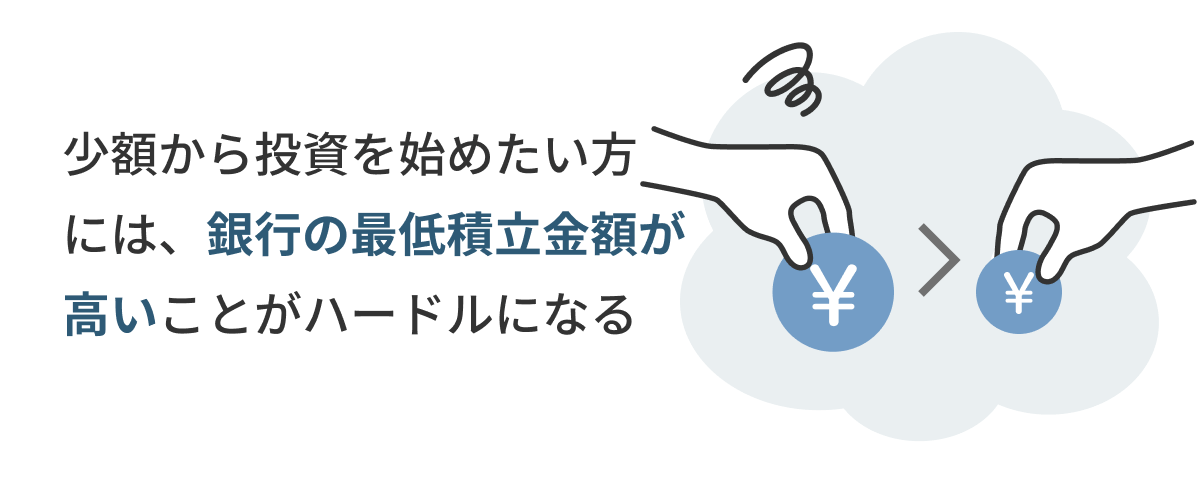
金融機関によって、新NISAの積立投資における最低積立金額が異なります。ネット証券では100円から積立可能な場合が多いですが、一部の銀行では1,000円からの設定となることがあります。少額から投資を始めたいと考えている方にとっては、銀行の最低積立金額が高いことがハードルになる可能性が考えられます。
では、具体的にどの程度の違いがあるのでしょうか?以下に、新NISAのつみたて投資枠における、主な金融機関の最低積立金額をまとめました。
| 金融機関名 | 最低積立金額 | 備考 |
|---|---|---|
| SBI証券 | 100円 | クレカ積立対応(Vポイント還元あり) |
| 楽天証券 | 100円 | クレカ積立対応(楽天ポイント還元あり) |
| マネックス証券 | 100円 | クレカ積立対応(マネックスポイント還元) |
| 松井証券 | 100円 | |
| auカブコム証券 | 100円 | au PAYカード積立対応 |
| 大和証券 | 1,000円 | |
| 野村證券 | 1,000円 | |
| SMBC日興証券 | 1,000円 | |
| みずほ証券 | 1,000円 | |
| 三菱UFJ銀行 | 1,000円 | 銀行窓口での取り扱い |
| 三井住友銀行 | 10,000円 | 銀行窓口での取り扱い |
| みずほ銀行 | 1,000円 | |
| ゆうちょ銀行 | 1,000円 | |
| りそな銀行 | 1,000円 |
- ※2025年6月時点、IFAナビ調べ
銀行でNISAを始めるメリットとは?
新NISAを銀行で始めることにはデメリットがある一方で、特に投資初心者にとってはメリットも存在します。銀行ならではのサービスや利便性は、金融機関選びの重要な判断材料となります。ここでは銀行でNISAを始めるメリットを解説します。
口座開設や手続きが簡単
普段から利用している銀行であれば、すでに口座を持っているため、NISA口座の開設手続きをスムーズに進められる場合があります。また、対面での手続きに慣れている方にとっては、オンラインでの手続きが主となるネット証券よりも安心して進められるでしょう。
窓口で直接相談できる
銀行の大きなメリットの一つは、店舗の銀行窓口で担当者に直接相談できる点です。投資に関する疑問や不安をface to faceで解消できるため、特に投資初心者の方にとっては心強いサポートとなります。ただし、前述したように、この銀行窓口での相談にも、商品選択肢の偏りなどのデメリットが潜んでいる可能性も理解しておく必要があります。
預金口座と一緒に管理しやすい
新NISA口座を普段利用している銀行で開設すると、預金口座とまとめて資産を管理できます。これにより、資金の移動が容易になり、家計全体の管理がシンプルになるという利便性があります。特にネット銀行と連携している証券会社では、こうした連携がスムーズな場合があります。
住宅ローン金利の優遇を受けられる可能性がある
一部の銀行では、NISA口座の開設や利用を条件に、住宅ローンの金利優遇を提供している場合があります。住宅ローンを利用している方や今後利用を検討している方にとっては、金利負担を軽減できる可能性がある点は銀行でNISAを始める大きなメリットとなり得ます。
このように、銀行でNISAを始めるメリットも存在します。
行き慣れた銀行で、担当者と対面で相談しながら進めたいと考えている投資初心者の方や、よく利用している銀行で資産を一元管理したいという方には銀行でのNISA制度活用がおすすめです。
銀行と証券会社はどう違うの?NISA比較!
新NISA口座を開設できる金融機関は、主に銀行と証券会社に分けられます。それぞれに特徴があり、ご自身の投資スタイルやニーズに合わせて選ぶことが重要です。
ここでは、銀行と証券会社の特徴を項目ごとに比較し、どちらが自分に合っているかを判断する材料を整理します。
| 比較項目 | 銀行 | 証券会社(特にネット証券) |
|---|---|---|
| 商品の種類 | 限られている(主に一部の投資信託) | 幅広い(投資信託・ETF・株式など) |
| 取引手数料 | やや高めの商品が多い傾向 | ノーロード・低コスト商品が豊富 |
| サポート体制 | 店舗窓口で対面相談可能 | 電話・チャット・メールなどオンライン中心 ただし、IFAを活用すればアドバイザーへの具体的な相談が可能に |
| 最低積立金額 | 1,000円以上の場合が多い | 100円から可能な場合が多い |
| スマホアプリ | 一部のみ対応・機能は限定的 | 高機能アプリを多数展開 |
| 株式・ETF投資 | 原則不可 | 可(NISA枠での直接投資も可能) |
- ※取扱商品数・サービスは2025年6月時点の情報に基づいています。
このように、選べる商品・手数料・機能面においては証券会社、特にネット証券が優位であることがわかります 。
銀行のメリット・デメリット
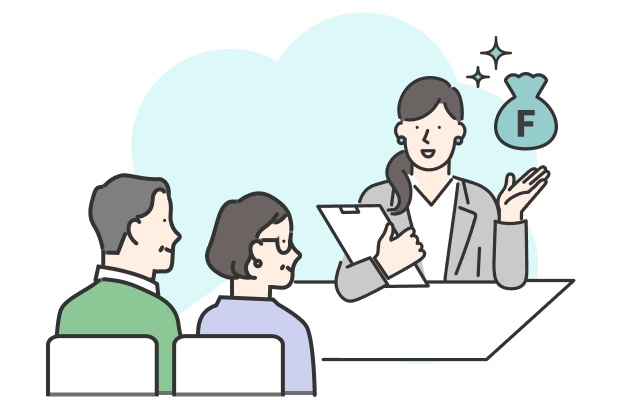
銀行でNISAを始める主なメリットは、普段利用している口座と連携しやすく手続きが簡単であること、そして何よりも窓口で担当者に直接相談できる安心感がある点です。特に投資初心者の方にとっては、対面で疑問や不安を解消できる点は心強いでしょう。
しかし、銀行では選べる投資信託の種類が限られていたり、株式やETFに投資できなかったりするデメリットがあります。また、金融商品の手数料が高い傾向にあること、最低積立金額が1,000円からと高いケースがあることもデメリットとして挙げられます。
証券会社(特にネット証券)のメリット・デメリット
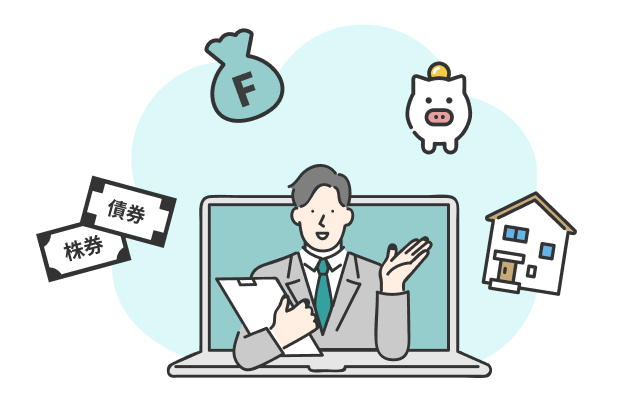
一方、ネット証券は、非常に多くの種類の投資信託や個別株、ETFを取り扱っており、投資の選択肢が格段に豊富です。また、購入手数料が無料の投資信託が多く、信託報酬も低コストの商品が豊富に揃っているため、手数料を抑えて効率的な運用を目指せます。さらに、100円から積立が可能な場合も多く、少額から投資を始めたい方にも適しています。クレジットカードでの積立によるポイント還元や、投資信託の保有額に応じたポイント付与など、お得なサービスを提供しているところも多く見られます。
しかし、ネット証券のサポートは電話やチャット、メールなどが中心となり 、自分で多くの商品の中から最適な投資先を選ぶ必要があるため、投資初心者にとってはハードルが高いと感じるかもしれません 。
提供されるサービスも金融機関によって異なります 。サポート体制についても違いがあります。銀行は店舗の窓口で対面での相談が可能で、担当者から直接アドバイスを受けたい方にとって安心感があります。ネット証券はオンラインや電話でのサポートが中心となりますが、FAQやチャットなど、デジタルでのサポート体制が充実しています 。
ネット証券でも相談ができる!NISAはIFAがおすすめ!
NISA口座の開設先を選ぶ際、銀行の対面サポートとネット証券の豊富な商品ラインナップや低コストはどちらも魅力的です。しかし、「対面で相談しながら、かつ手数料を抑えて幅広い商品から選びたい」という両方のニーズを満たす選択肢があります。それが、IFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)の活用です。
IFAは特定の金融機関に属さない独立した専門家であり、ネット証券の豊富な商品ラインナップの中から、お客様一人ひとりの投資目標やリスク許容度に合わせた最適な商品を、中立的な立場からアドバイスしてくれます 。基本的に相談料は無料です。(有料のIFAも一部存在します)
IFAへの相談が無料なのは、IFAがお客様から直接相談料をいただくのではなく、提携先の金融機関から手数料を受け取るビジネスモデルだからです。そのため、お客様は費用を気にすることなく、中立的な専門家のアドバイスを受けることができます。
IFAに相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 豊富な選択肢からの最適な提案
ネット証券の幅広い商品の中から、あなたに本当に合った商品を選定してもらえます 。 - 専門家による具体的なアドバイス
投資に関する疑問や不安を解消しながら、銘柄選定からポートフォリオの構築、長期的な資産運用まで、具体的なサポートを受けられます 。 - 中立的な立場
特定の金融機関の営業方針に縛られることなく、あなたの利益を最優先したアドバイスが期待できます 。
ネット証券の利便性と専門家による個別サポートの両方を得たい方にとって、IFAを活用したNISA運用は非常に有効な選択肢となります 。
ただし、金融庁ホームページによると日本国内にIFA(=金融商品仲介業者)は600以上存在し(令和7年5月末時点)、それぞれが得意とするアドバイスや特徴、提携している証券会社などの違いを持っています。そのため、自分一人でNISAの相談に最適なIFAを探すのは大変な作業になるでしょう。
そんな時は、IFAナビをご利用ください。IFAナビは日本初のIFA法人検索機能を持つ「IFA選びのサポート」サイトです。IFAナビの『資産運用の無料相談窓口』は、ご利用者様一人一人のご希望に合わせて、最適なIFAを無料でご紹介するマッチングサービスをご提供しています。
関連記事はこちら
すでに銀行でNISA口座を開いている場合はどうするべき?
「もう銀行で新NISAを始めてしまったけど、今から証券会社に変えるのは遅い…?」
そんな不安を抱く方も少なくありません。
結論から言えば、金融機関の変更は可能です。ただし、年度途中の変更はできず、変更手続きには書類のやり取りと一定の期間(1〜2か月)がかかるため、今後の方針を早めに見直すことが大切です。
現在の銀行NISAを継続するべきか、証券会社に切り替えるべきかを判断する際は、以下の点を基準にしてみましょう:
- 今のNISAで投資している商品に満足しているか?
- 手数料や信託報酬が割高でないか?
- 将来的に株式やETFにも投資したくなる可能性はあるか?
もし少しでも「不安」「見直したい」と感じる点がある場合は、NISA口座の証券会社への移管も検討しましょう。
NISAの金融機関はここで選ぶ!選び方のポイントを紹介
NISAのメリットを最大限に活かし、効率的な資産形成を目指すためには、どの金融機関で口座を開設するかが非常に重要です。ここでは、NISAを始める金融機関を選ぶ際の重要な3つのポイントを解説します。
自分が投資したい商品を取り扱っているか
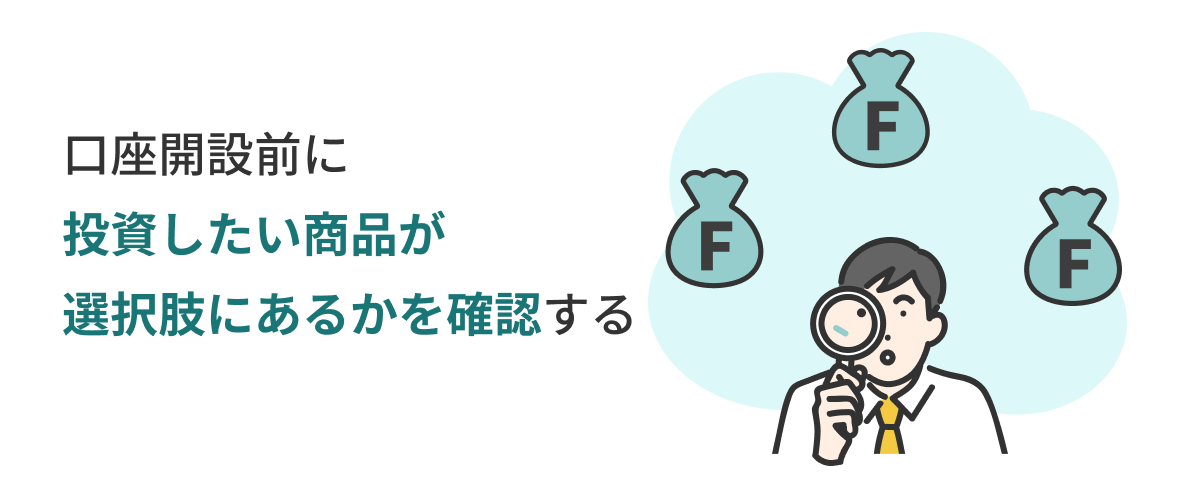
NISA制度では、各金融機関が独自の投資商品ラインナップを提供しています。口座開設前に、あなたが「どんな商品に投資したいのか」を具体的にイメージし、その商品が選択肢にあるかを確認することが大切です。
例えば、
- 「つみたて投資枠」で低コストのインデックスファンドに積立投資したい場合
eMAXIS SlimシリーズやSBI・Vシリーズといった人気の低コストファンドが、希望する金融機関で取り扱われているかを確認しましょう。金融機関によっては、つみたて投資枠の対象商品数が大幅に異なる(本記事の「選べる投資信託の種類が少ない」で詳細を解説しています)ため、選択肢の豊富さも重要な要素です。 - 「成長投資枠」で個別株やETF(上場投資信託)にも投資したい場合
銀行では原則として個別株やETFの取り扱いがありません。これらの商品に投資したい場合は、証券会社を選ぶ必要があります。
NISA口座は一人につき一口座しか開設できません。金融機関の取扱い商品を確認することが、後悔しない選び方の第一歩となります。
口座開設などNISAを始めるまでの手続きが理解できそうか
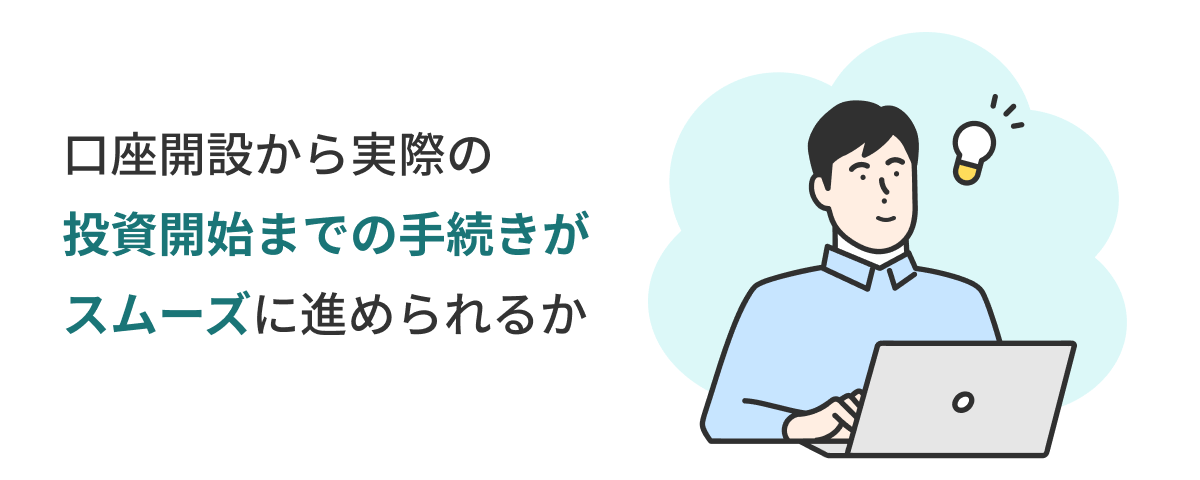
NISAを始める上で、口座開設から実際の投資開始までの手続きがスムーズに進められるかも大切なポイントです。
- オンライン手続きのわかりやすさ
ネット証券の場合、口座開設からNISA設定までをオンラインで完結できるのが一般的です。ウェブサイトやアプリの操作性が直感的で、分かりやすい説明があるかを確認しましょう。 - 対面サポートの有無
銀行や一部の対面証券では、店舗の窓口で担当者に直接相談しながら手続きを進めることができます。投資初心者で、複雑な手続きに不安を感じる場合は、対面でのサポートが充実している金融機関を検討するのも良いでしょう。 - 必要書類の準備
本人確認書類やマイナンバーカードなど、口座開設に必要な書類について、事前に準備がしやすいかどうかも確認しておきましょう。
運用中に最適なサポートを受けられそうか
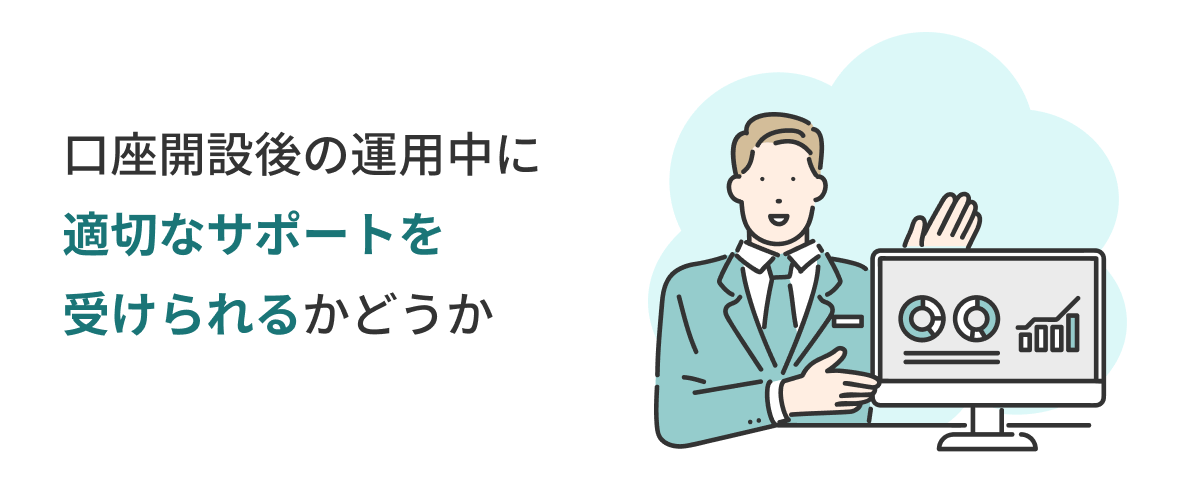
NISAは長期的な視点での投資が基本となるため、口座開設後の運用中に適切なサポートを受けられるかどうかも重要な要素です。
- 情報提供の充実度
投資判断に役立つ市場情報、経済ニュース、投資教育コンテンツなどが豊富に提供されているかを確認します。 - ツールの使いやすさ
資産状況の確認、積立設定の変更、ポートフォリオのリバランスなどを行うためのウェブサイトやスマホアプリの機能性・操作性をチェックしましょう。 - 相談体制
疑問や不安が生じた際に、電話、チャット、メールなどで迅速かつ的確なサポートを受けられるかを確認します。
よくある疑問Q&A(変更手続き・両方持てる?など)
新NISAや金融機関選びに関して、多くの方が抱える疑問についてQ&A形式で解説します。
Q.NISA口座を銀行からネット証券に変更するのは大変?
A.
新NISA口座は一人につき一口座しか開設できません。2023年までの旧NISA口座を持っている場合、通常は同じ金融機関で自動的に新NISA口座が開設されますが、異なる金融機関で開設したい場合は手続きが必要です。金融機関を変更する場合、現在NISA口座を開設している金融機関から「勘定廃止通知書」または「非課税口座廃止通知書」を受け取り、新しい金融機関に提出する手続きが必要となります。この手続きはそこまで大変とは言えませんが、時間がかかる場合があるのが難点です。NISA口座を移す場合は、余裕をもって行うことが推奨されます。なお、一度金融機関を変更すると、原則としてその年は再度変更することはできません。また、変更前のNISA口座で保有している商品を、変更後の新しいNISA口座に移すことはできない点に注意が必要です。
Q.銀行で勧められた投資信託はそのまま続けてもいい?
A.
銀行で勧められた投資信託をそのまま続けるべきかは、その商品の信託報酬やご自身の投資目標、そしてポートフォリオ全体とのバランスによって判断が異なります。もし手数料が高い商品であったり、ご自身の目指すリターンと乖離していると感じたりする場合は、見直しを検討することをおすすめします。必要であれば、中立的な立場のアドバイスを受けられるIFAに相談し、現状の投資信託があなたにとって最適かどうかを確認してみるのも良いでしょう。
Q.NISAは銀行と証券会社、両方持つことはできる?
A.
残念ながら、新NISA口座は一人につき一口座しか開設できません。そのため、銀行と証券会社の両方でNISA口座を持つことはできません。ご自身にとって最適な金融機関を一つ選び、そこでNISA口座を開設する必要があります。
Q.お世話になっている担当者が「うちが一番いい」と言うけど信じていい?
A.
金融機関の担当者は、取扱商品やサービスに詳しいため、NISAに関するアドバイスを求めるのは自然なことです。しかし、担当者には売上や販売目標がある場合が多く、必ずしも顧客の利益を最優先した提案ばかりとは限りません。そのため、「うちが一番いい」という言葉を鵜呑みにせず、この記事で解説した商品の品揃え、手数料、サポート体制などの比較ポイントを参考に、ご自身でも情報を集めて判断することが重要です。中立的な立場からアドバイスを得たい場合は、特定の金融機関に属さないIFAへの相談も有効な選択肢となります。
まとめ銀行でNISAの積立運用はやめた方が良い?結論とおすすめの相談先
「銀行でNISAの積立運用はやめた方が良い?」という疑問に対し、この記事ではそう言われる理由、メリット・デメリット、そして金融機関選びのポイントを詳しく解説してきました。
結論として、NISAを最大限に活用し、自身の投資目標に合った多様な商品から選び、手数料を抑えて効率的に資産形成を目指すのであれば、多くのケースで銀行よりもネット証券の利用がより有利な選択肢となるでしょう。
銀行は、口座開設の手軽さや対面での相談、既存の預金口座との連携といったメリットを提供しますが、その一方で、取扱商品の選択肢が限られ、株式やETFへの投資ができないことなどがデメリットとして挙げられます。
もし、あなたがこれからNISAを始めるにあたり、
- より多くの商品から自身の投資戦略に合ったものを選びたい
- 運用コストをできるだけ抑えたい
- 将来的に個別株式やETFへの投資も視野に入れている
- オンラインでの手続きや管理に抵抗がない
と考えているのであれば、ネット証券が適している可能性が高いです。
すでに銀行でNISA口座を開設している場合でも、金融機関の変更は可能です。ただし、手続きに時間と手間がかかるため、現在の運用状況や将来的な投資ニーズをしっかり見極めることが重要となります。
「なるべく多い選択肢から投資商品を選びたい」、「専門のアドバイザーに相談して、自分に最適なNISA運用戦略を立てたい」といった不安や希望を抱えている場合は、特定の金融機関に属さず中立的な立場からアドバイスを提供するIFA(独立系ファイナンシャルアドバイザー)への相談がおすすめです。
IFAは、あなたのライフプラン全体を見据え、NISA口座選びから最適な商品選定、さらには他の資産運用についても総合的な視点からサポートしてくれます。
IFAナビでは、あなたのニーズに合ったIFAを無料でご紹介していますので、ぜひ積極的にご活用ください。
資産運用でお悩みの方へ
無料相談サービスとは?
記事一覧
- NISA・iDeCoの活用術
-
-

NISA・つみたてNISA・新NISAの相談先はどこ?おすすめ3選と選び方のコツを解説
-
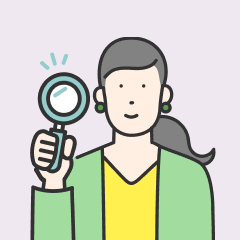
新NISAはデメリットしかない?従来の制度との違いや運用のコツを解説
-

【比較表あり】銀行でNISAはやめたほうがいい?4大理由とおすすめ相談先、メリット・デメリットを解説
-
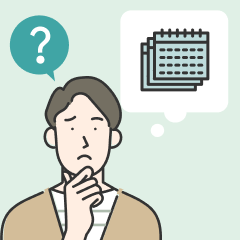
NISAを始めるタイミングはいつにすべき?手続きや運用のポイントを解説
-
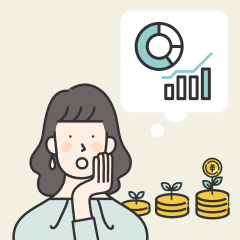
新NISAは月いくら投資すべき?平均額や投資金額の決め方を解説
-
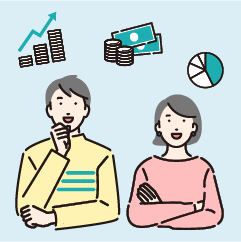
新NISAの成長投資枠を最大限活用!月間上限や非課税限度額を分かりやすく解説
-

新NISAは売却後に枠復活するって本当?仕組みや活用方法を解説
-
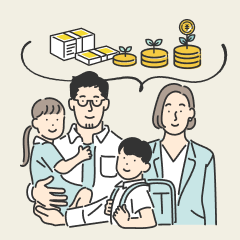
ジュニアNISA終了後に最適!新NISAで子どもの教育資金を賢く準備する方法
-

確定拠出年金とは?入らない方がいいって本当?その理由と加入するメリットを解説
-

iDeCoの節税効果をシミュレーション!メリットを感じられる人とは
-

【図解あり】iDeCoで月1万円の積立は意味ない?シミュレーション結果と損しないための注意点を解説
-
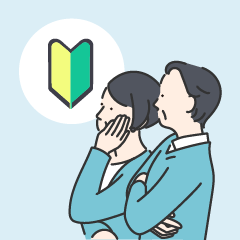
50歳から始める資産形成!iDeCoとNISAはどっちがお得?失敗しない運用のコツ
-

iDeCo(イデコ)の相談窓口はIFAがおすすめな理由とは?メリットなども解説
-
- 資産運用の始め方・相談ガイド
- 投資の基本・はじめての資産運用
- ファイナンシャルプランナー(FP)相談のポイント
- 退職・老後など人生イベント別
資産形成対策 - 年代別のおすすめ運用方法
- 資産額別のおすすめ運用方法
- 保険の見直しや資産運用との関係
- 資産運用のよくある失敗事例と
その対策 - 富裕層のための資産運用・
節税対策